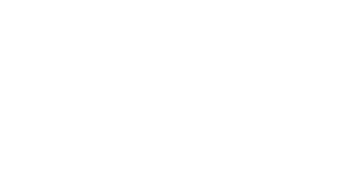前回はダイキンエアコンの3つの特徴をダイキンのショールーム“フーハ東京”で、空調営業本部 事業戦略室の森上群平さんにお話しをうかがいましたが、今回はダイキンエアコンの省エネの秘密についておうかがいします。
---猛暑が続き、エアコンを昼夜問わず稼働させていて電気代の心配をしている方が多いと思います。そこで、ダイキンエアコンの省エネや節電に対する取り組みをおうかがいしたいのですが---
ダイキン うるさらXは、高い省エネ性を実現しており、目標年度2027年の省エネ基準も多くのラインアップで100%以上を達成しています(一部能力帯を除く)。省エネ性は電気代にも直結する重要な数値であるため、様々な努力と工夫をおこなっています。

--実際に、いまあるダイキンエアコンでは年間の電気消費量はどれくらいかかるものなのでしょうか。最上位機種とそうでないものとではかなり差が出るものなのでしょうか---
ダイキンでは、各ラインアップと能力帯ごとに、年間でどのくらいの電力を使うのか、期間消費電力量を一覧にした下敷きも作成しており、イニシャルコストだけでなく、ランニングコストによる比較もできるようにしています。例えばリビング12畳のお部屋のエアコンを買い替える場合、今現在の一番お手頃な機種Eシリーズだと年間の消費電力量が1390kWhになります。
一方で、最上位機種RXだと年間の消費電力量が1032kWhです。
最上位機種RXと一番お手頃な機種Eとを比べると、約25%ほど最上位機種RXの方が省エネなんです。
さらに、期間消費電力量に、電力料金目安単価の31円/kWh(税込)(令和4年7月改定)(全国10電力平均)※をかけると、電気料金目安が計算できます。
年間の電気代(目安)の計算式 ※当社採用の計算式の場合
| E機種 | 年間消費電力量 1390kWh × 電力料金目安単価 31円/kWh = 約43000円 |
| RX機種 | 年間消費電力量 1032kWh × 電力料金目安単価 31円/kWh = 約32000円 |
→ RXの方が年間で1万1千円もお得に!
---1年で1万円お得なら10年使えば10万円もお得ということになりますね。そうすると最初にエアコン本体の値段が高くても、省エネ達成率の高いものを買った方が長い目で見ればいいかもしれませんね—
基本的には10年で交換を推奨しておりますが、内閣府のデータでは、おおよその使用年数は14年程度です。そこで先ほどの12畳用エアコンのRXシリーズとEシリーズの期間消費電力量で計算すると、14年で約5,012kWhもの差がでます。さらに、いまは電力料金目安単価は31円/kWhと公表されておりますが、電気料金単価は年々上がる傾向にあり、今後さらに電気料金は高くなることが予想されます。そうすると、この差はもっと開いていくことが予想されます。どうしても初期費用に目を奪われがちですが、今後の電気料金の値上げなどを考慮に入れて、トータルランニングコストを計算することが大事です。しかも14年間ずっと快適な空気環境で過ごせるのですから、お客様に自信を持って最上位機種をおすすめしています。
14年間使用した場合の電気代(目安)の計算式 ※当社採用の計算式の場合
| E機種 | 年間の電気代 約43000円 × 使用年数14年 = 約602000円 |
| RX機種 | 年間の電気代 約32000円 × 使用年数14年 = 約448000円 |
→ RXの方が14年間で約15.4万円もお得に!
---確かに今後の電気代の値上がりも考慮すべきですね。いまのお話で、省エネ達成率の高い上位モデルの方が高性能でありながら節電もできてコスパもいいということがよくわかります。では、そのような高い省エネ性を実現するために、どのような技術が使われ、どのような工夫がなされているのでしょうか---
まず、エアコンで消費電力量が一番多いのは圧縮機になります。ダイキンのエアコンは、低速でもすごく省エネで動けるというのが寄与する部分としては一番大きいです(詳しくは前回の記事へ)。
また、消費電力量を抑えようとすると熱交換効率を上げることが重要です。つまり、少しの電力でできるだけ多くの空気を冷やしたり暖めたりできれば省エネにつながるわけです。そして、どのメーカーでもエアコンの最上位機種は、たいてい室内機も室外機も大きいのですが、それは熱交換の面積を増やして一度に多くの空気の冷やしたり暖めたりするためです。内部を見てもらうとわかるのですが、列が多かったり大きさが全然違うんです。他に比べて省エネ性が高い上位機種の室内機は、熱交換器の面積を稼いでいるから大きいんですね。
 上:上位機種うるさらXの室内機断面
上:上位機種うるさらXの室内機断面
下:スタンダードモデルEシリーズの室内機断面
上が大きいが列が多く面積も広いのがわかる
---室内機はコンパクトなものの方が電力を消費しないイメージがあったので、大きい方が省エネ性が高いのは意外でした。熱交換器の面積を広く取って省エネを図っているのは他社も同様ということですが、ダイキンならではの省エネの技術や工夫は何がありますか---
夏場は湿度が高くなります。エアコンは自動運転だと冷房と除湿を切り替えていくのですが、その約6割が除湿運転※1になります。そして、簡単に言うと、除湿は冷たいペットボトルを置くと水滴が付くのと同様に、結露をさせて冷たい空気を室内に送り、水分を取り除くということをエアコンの中でやっています。普通はただ冷やすだけですが、ダイキンの場合はこの中を流れる冷媒の量をコントロールできるんですね。それを“リニアコントロール”と呼んでいます。さらに、最上位機種のRX、AX、DXシリーズは、さらら除湿(リニアハイブリッド方式)※2で、状況に合わせて除湿方式を切替え、お部屋の温度維持しながら快適なしつどコントロールを実現しております。
※1:ダイキン調べ 自動運転中の各運転モードの出現率を分析 対象機種 RX・AX 39,273台分 対象期間 2021年4~9月 条件:AI快適自動運転中の運転モード ※2:RX・AXシリーズ9.0kW、DXシリーズ8.0kWを除く

この“リニアコントロール”は、ダイキンが業界で初めて家庭用エアコンに“多段階電子膨張弁”を採用したことで実現しました。
例えば梅雨のときなど暑くて湿度の高いときは全体を使って冷やして除湿しますが、それほど気温も湿度も高くないときは前列だけ使うなど、必要なときに必要な分だけ冷媒をコントロールできるんです。それによって無駄な消費を抑えて省エネに寄与しているんです。ここはダイキンが秀でているところだと思います。
これを備えた最上位機種のRX(うるるとさらら)は快適で省エネかつ除湿に強いので、この夏は特におすすめです。
 多段階電子膨張弁:圧縮機と除湿弁を合わせてコントロール。
多段階電子膨張弁:圧縮機と除湿弁を合わせてコントロール。
消費電力を抑えながら室温変化させずに除湿運転を行える。
---熱交換器の中を細かくコントロールできるんですね。エアコンの中にそんな技術が詰まっているなんて初めて知りました。やはり、エアコンは長い付き合いになるので、技術や機能を理解して選びたいですね---
今回はダイキンエアコンの省エネの秘密についてのお話でしたが、次週は、エアコンとの上手な付き合い方についておうかがいします。